『光が死んだ夏』は、累計300万部突破&「このマンガがすごい!2023」オトコ編第1位を獲得した話題作。
でもその人気ゆえに「他の作品に似てる」「パクリじゃない?」って噂が出ちゃってるんですよね。
実はこの作品、哲学的テーマやpixiv短編の原点、SNSでの拡散までいろんな要素が重なってできた唯一無二の物語なんです!
- ✔ 「光が死んだ夏」に囁かれる“パクリ疑惑”がどこから生まれたのか、その論点の源流
- ✔ 『チェンソーマン』『Another』『寄生獣』などと比較される具体的な“似てると言われるポイント”の中身
- ✔ 商業化前に投稿されていたとされるpixiv短編(プロトタイプ)の概要と、現行連載との違いの見どころ
- ✔ BL色の強かった初期版から“ブロマンス×青春ホラー”へと変化した経緯と読者層の広がり方
- ✔ 哲学的思考実験「スワンプマン」が物語に与えるテーマ的インパクトと、読む時の着眼点
- ✔ 三重弁を参考にした方言や作者の原体験が“田舎の不穏さ”を増幅させる演出のディテール
- ✔ 活字フォントの擬音など独特のホラー表現が“既視感と新しさ”を同時に生む仕組み
- ✔ TikTokやボイスコミック拡散で起きた二次創作ブームと、作品理解が深まる楽しみ方
光が死んだ夏はパクリではない!疑惑の真相を解説
『光が死んだ夏』って、今やSNSでも大人気で「読んだら沼る」と噂の作品なんだけど、その分「これってパクリじゃない?」なんて声も出ちゃってるんです。
でも、実際に内容を追ってみると、他作品との共通点はあっても独自性がしっかりあるんですよ。
ここでは、よく名前が挙がる『チェンソーマン』『Another』『寄生獣』との比較をしながら、その真相をチェックしていきますね!
チェンソーマンとの比較と相違点
ネットでよく言われるのが、『チェンソーマン』とキャラクター配置が似てるんじゃないかって話です。
『光が死んだ夏』では黒髪で真面目なよしきと、少しズレたお調子者タイプのヒカルのコンビ。
これが『チェンソーマン』のアキとデンジに似てるって言われてるんですけど、実際は王道的なバディ設定なんですよ。
真面目キャラと破天荒キャラの組み合わせは昔からある構図で、ここだけ見て「パクリ」と断定するのはちょっと早計なんです。
むしろ『光が死んだ夏』は、田舎の閉鎖的な集落という舞台や、心理的なホラー演出で全然違う怖さを描いています。
Another・寄生獣との共通点と違い
『Another』や『寄生獣』とも似てるって声があります。
『Another』だと「閉鎖的なコミュニティに人ならざる者が入り込む」設定が共通してるし、『寄生獣』だと「日常に異物が紛れ込む」テーマが近いんですよね。
でも決定的に違うのは、『光が死んだ夏』は謎解きやバトルよりも“人間関係の歪み”にフォーカスしているところ。
よしきが抱える喪失感や、ヒカルへの依存が怖さの核心になっていて、この点は他のホラー作品とは一線を画してます。
人気作ゆえにパクリと疑われやすい理由
じゃあ、なんでこんなに「パクリじゃない?」って声が出るのかっていうと、これは人気作の宿命なんです。
大ヒットする作品って、どうしても過去の名作と普遍的なテーマを共有しがちなんですよね。
しかも『光が死んだ夏』は2024年には累計300万部突破の大ヒット。注目される分、似てる要素があるとすぐに話題になっちゃうんです。
でも、読み込むと「パクリではなく独自の切り口」ってすぐに分かります。

光が死んだ夏の元になった漫画や短編作品
『光が死んだ夏』には、商業化される前にpixivやTwitterで公開されていた短編版があったのをご存じですか?
そこでは、今よりもBL色が強い人外作品として描かれていて、その後の大ヒットにつながるきっかけになったんです。
ここからは、その短編の存在や商業化による変化、さらにTikTokでの人気爆発までをまとめてみます!
pixivに投稿された創作BLが原点
作者のモクモクれん先生が最初に描いた『光が死んだ夏』は、pixivで公開されていた創作BL短編でした。
ジャンルは人外BL。親友が別の存在にすり替わってしまうというテーマは、すでにここで登場していたんです。
当時の読者の記憶では、とにかく切なくて不気味な雰囲気が強かったそうですよ。
商業化でBL要素からブロマンスへ変化
その後、SNSで話題になったことをきっかけにKADOKAWAから商業連載が決定。
ジャンルはBLから「青春ホラー」「ブロマンス」へと変化しました。
直接的な恋愛要素は薄れたけど、よしきとヒカルの関係性はむしろ強調され、友情とも依存とも愛情ともつかない濃密な感情が描かれるようになったんです。
この変化が、BLに馴染みのない読者層からの支持にもつながりました。
TikTokでの拡散と二次創作ブーム
さらに大きな追い風になったのが、TikTokでの拡散。
ボイスコミックで登場した「めっちゃ好き」というセリフがバズり、コスプレ動画や二次創作が一気に広まりました。
特にZ世代には「この関係性エモすぎ!」と刺さり、ブームが加速していったんです。
個人創作から商業化、そしてSNS発のムーブメントへ。まさに現代的な成功パターンですね。

削除された幻のプロトタイプ版とは?
ファンの間では、いまや読めなくなった『光が死んだ夏プロトタイプ』が存在したって噂が有名なんです。
これはpixivに投稿されていた初期短編で、商業化される前に削除されちゃったんですよね。
ここでは、そのプロトタイプの中身や連載版との違い、さらに噂されるラブシーンやクトゥルフ要素について掘り下げます!
pixivに存在した初期短編の噂
「プロトタイプ版」はpixivに投稿されていたものの、現在は削除されていて正規の手段では読めません。
ただ、当時読んだファンの記憶や断片的なキャプチャから、確かに存在していたと言われています。
今の連載版の核となる設定はすでに描かれていたみたいですが、雰囲気はよりストレートなホラーだったそうです。
プロトタイプと連載版の違い(恐怖表現・設定)
プロトタイプでは、不条理ホラー感が前面に出ていたのが特徴。
連載版のような緩急ある展開や心理描写は薄く、代わりに唐突で不気味な展開が多かったみたいです。
さらに、村の風習や方言設定も曖昧で、空気感重視の描写だったといわれています。
今の作品はキャラの家庭背景や舞台がより詳細になり、心理的な怖さが増しているんですね。
ラブシーンやクトゥルフ要素の憶測
ファンの間で語られている噂のひとつが「幻のラブシーン」。
よしきとヒカルがもっと直接的に親密だったのでは?っていう話です。
また、当時のタグにクトゥルフ要素を示す言葉があったとも言われていて、ホラー好きの作者らしい影響が色濃かったのかもしれません。
真相は闇の中ですが、その曖昧さこそ「幻の短編」としてファンを惹きつけているんです。

光が死んだ夏の独自性の源泉
じゃあ、『光が死んだ夏』を唯一無二にしてる要素って何?って気になりませんか?
実はこの作品、哲学的な思考実験や作者の実体験、独創的な演出がミックスされてできてるんです。
ここでは、その独自性の秘密を3つの視点から掘り下げますね!
哲学的テーマ「スワンプマン」と同一性の問題
一番有名なのがスワンプマン理論。
雷で死んだ人と寸分違わぬコピーが現れたとき、その存在を「本人」と呼べるのか?という哲学の問いなんです。
これはまさに光とヒカルの関係そのもの。
読者は「偽物と分かってても、そばにいて欲しい」という切実な感情に触れて、心を揺さぶられます。
三重弁をベースにした舞台設定と作者の原体験
舞台の方言は三重弁を参考にしているのも有名な話。
関西弁と違う微妙なニュアンスが、閉鎖的でリアルな雰囲気を演出してるんです。
しかも作者の祖母の集落での体験が舞台の基盤になっているので、描写がすごく生々しいんですよ。
「えらい(疲れた)」なんて方言のチョイスも作品の世界観にピッタリ!
活字フォントを使った独特のホラー演出
そしてもう一つの独自性は、活字フォントの擬音。
普通の漫画だと手書きで描く擬音を、あえて冷たい明朝体で表現しているんです。
「ギ…」「ズル…」みたいな無機質な文字が、日常シーンに突然入り込むことで、不気味さが一気に増すんですよ。
これって作者がホラー映画好きだからこそ生まれた表現で、読者の視覚と聴覚に同時に訴えかける独特の怖さを演出しています。
まさに唯一無二の表現技法ですね!

光が死んだ夏 パクリ疑惑と元になった漫画のまとめ
ここまで見てきたように、『光が死んだ夏』には確かに他作品と共通する要素はあります。
でも、それはホラー作品や青春漫画が持つ普遍的な型であって、単なる模倣とは全く違うんです。
むしろpixiv短編から始まり、哲学的テーマや独自演出を組み合わせて進化したことで、今の人気を勝ち取ったんですよね。
光が死んだ夏のパクリ疑惑の答え
結論から言うと、『光が死んだ夏』はパクリではなく独自のオリジナル作品です。
『チェンソーマン』『Another』『寄生獣』と比較されても、テーマや焦点が全然違います。
むしろ共通点があるからこそ、多くの読者が「既視感あるけど新しい!」と感じて引き込まれたんです。
元になった短編やプロトタイプの存在
作品の原点には、pixivに投稿された創作BL短編や、削除されたプロトタイプ版がありました。
これらが基盤となって、商業連載で青春ホラーへと発展していったんです。
つまり『光が死んだ夏』は、作者の創作意欲とSNS文化から生まれた現代的な成功例なんですよ。
読者が今楽しむべきポイント
だからこそ、今読むべきなのは「パクリかどうか」よりも、よしきとヒカルの関係性や、独特のホラー演出を味わうこと。
さらにTikTokや二次創作を通じて広がったムーブメントも一緒に楽しむと、作品の魅力が倍増します。
『光が死んだ夏』は疑惑を超えて、すでに新しい時代のホラー青春漫画として確立されているんです。

- ★ 『光が死んだ夏』は他作品と類似点はあるが、独自のテーマと表現によりオリジナリティを確立している
- ★ 『チェンソーマン』『Another』『寄生獣』との比較はあるが、物語の焦点は異なるためパクリではない
- ★ 原点はpixivに投稿された創作BL短編で、商業化でブロマンス要素を強調した形に進化した
- ★ 削除された“プロトタイプ版”はホラー色が強く、連載版との違いがファンの間で語り継がれている
- ★ 哲学的テーマ「スワンプマン」が物語の核心に据えられ、存在と同一性をめぐる問いを提示している
- ★ 舞台は作者の原体験を基盤に三重弁を取り入れたリアルな集落描写で構築されている
- ★ 活字フォントの擬音表現など独創的な演出が、独特の不気味さと恐怖を生み出している
- ★ TikTokでの拡散や二次創作ブームにより、若年層を中心に爆発的な人気を獲得した

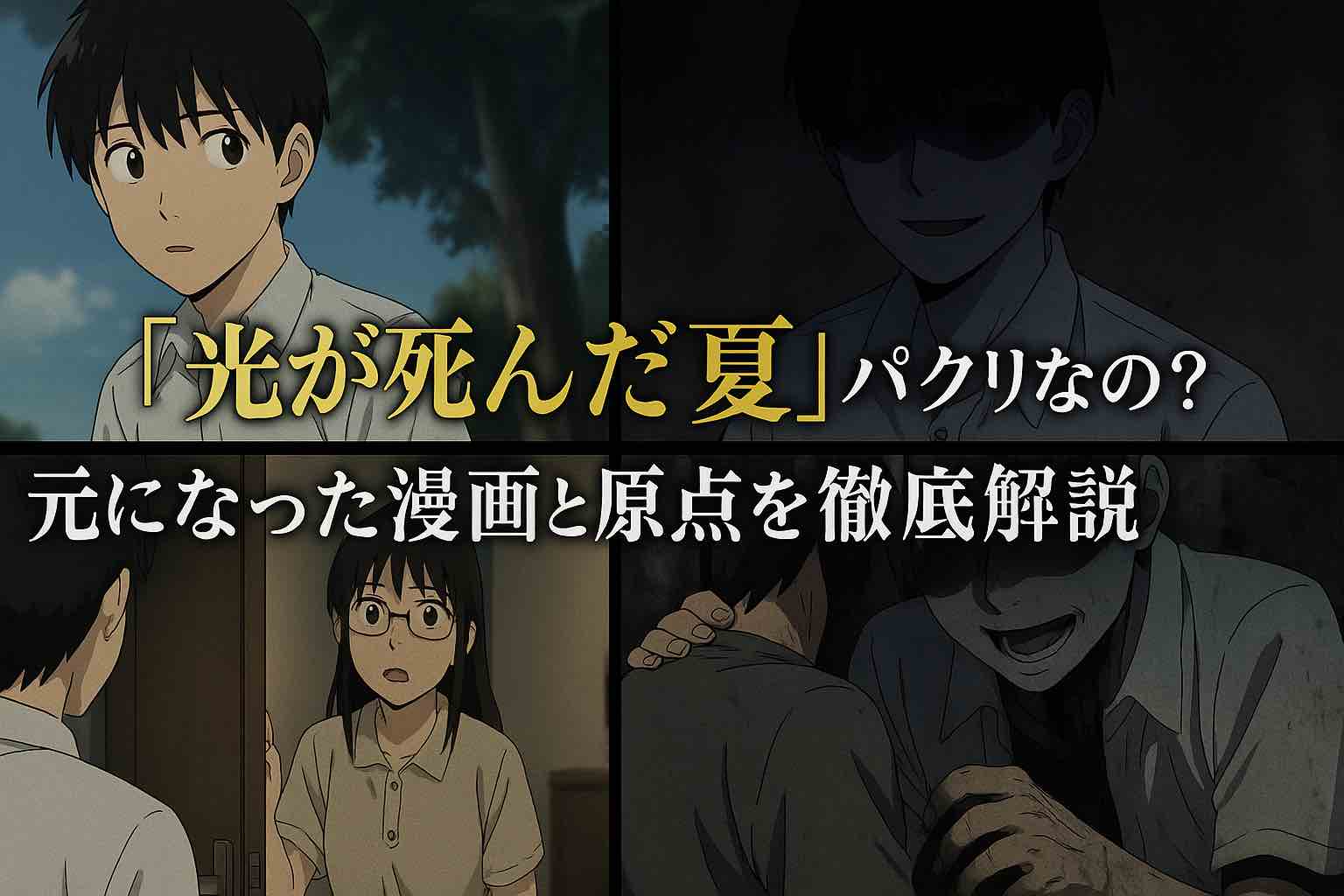


コメント