細田守監督の代表作『バケモノの子』は、2015年の公開から10年経っても多くの人の心に残る作品ですよね。
でも実は、ネット上では「感動した!」という声と同じくらい「ひどい」「つまらない」という意見もあるんです。後半の展開やキャラクターの描き方に違和感を感じた人が多かったみたい。
そこで今回は、そんな賛否両論の『バケモノの子』のネタバレ感想を中心に、「ひどい」と言われる理由と、実はそこに隠された深いテーマや感動の真実を、アニメ好き女子の視点でじっくり語っていきます!
- ✔ 「ひどい」「合わない」と感じる人が挙げる具体的なポイントと、その背景にある物語構成・キャラクター描写の特徴
- ✔ 熊徹と九太の師弟関係や“もうひとつの親子愛”がどのように描かれているかを整理しながら読み解ける視点
- ✔ チコや楓の役割、「楓いらない」と言われる理由と、その裏にあるテーマ性・象徴性の理解につながる考察ポイント
- ✔ クジラと小説『白鯨』モチーフが示す「心の闇」と「自己との対話」のメッセージを物語全体から読み取る手がかり
『バケモノの子』が「ひどい」と言われる3つの理由
公開から10年が経った今でも話題に上がる映画『バケモノの子』。でも、SNSやレビューサイトを覗いてみると「ひどい」「つまらない」という声もちらほら見かけます。
じゃあ、いったいどのあたりが“ひどい”って言われてるの?と思う方も多いはず。今回は、後半の展開の雑さやキャラクター描写の浅さなど、主に3つの理由をもとに分析していきます。
ネガティブな感想が集まる背景をしっかり整理しながら、「でも実はそこに意味があったのでは?」という視点も交えて紹介しますね。
① 後半の展開が急ぎすぎて感情移入できない
まず一番多いのが、「後半が駆け足すぎてついていけない」という意見。前半では熊徹と九太(蓮)のぶつかり合いと絆の形成がすごく丁寧に描かれているんですよね。
でも、成長した九太が人間界に戻るあたりから、楓との出会い、父との再会、一郎彦の暴走とイベントが一気に畳みかけてきます。心理描写も浅く、「え、いつの間に?」と感じてしまう人も多かったようです。
実際、Filmarksやシネマヒッツでも、「詰め込みすぎ」「感情が追いつかない」との声が目立ちました。テンポは悪くないけど、物語の深みをもう少し味わいたかった…という感想、わかります。
② 期待外れの結末と熊徹の消失
次に、「せっかく成長したのに別れで終わるなんて悲しい」という意見も多いです。九太を育てた熊徹が神に転生して剣になるシーンは、感動的だけどショッキングでしたよね。
観る人によっては「ここで終わり!?」「熊徹と九太が一緒に生きる未来を見たかった」という気持ちになるのも当然です。家族愛の物語として観ると、希望の余韻よりも喪失感が強く残ってしまったのかもしれません。
ただ、熊徹が“剣”として九太の心に生き続ける展開は、「親は姿を消しても、心で支える存在」というメッセージとも受け取れます。ここをどう感じるかで、評価が大きく分かれた印象です。
③ 一郎彦の闇落ちに説得力が欠けた
そしてもうひとつ、「一郎彦がなぜ闇に堕ちたのかよく分からない」という声。彼は立派な父・猪王山を尊敬していましたが、実は自分が人間だったという秘密に苦しんでいたんです。
でも、映画ではその内面の葛藤があまり描かれず、いきなり「闇に飲まれて暴走!」という流れに。確かに唐突でしたね。小説版ではもう少し詳しく説明されていますが、映画だけ見た人には動機が弱く感じられたのも納得です。
とはいえ、彼の「闇」は人間誰しもが持つ心の弱さの象徴でもあります。だからこそ九太の「闇を乗り越える」姿が際立っていたとも言えます。

「ひどい」とは逆に高評価を得たポイント
一方で、「ひどい」と言われる声の裏には、めちゃくちゃ熱い支持もあるんです。実際、Filmarksでは平均スコア★3.7と高評価。観る人によって“刺さるポイント”が違う作品なんですよね。
ここでは、作品の中でも特に好評だった師弟愛・世界観・音楽演出の3つに注目してみましょう。
「ひどい」と感じた人も、もう一度この視点で観ると、印象がガラッと変わるかもしれません!
① 熊徹と九太の師弟関係に描かれる“もうひとつの親子愛”
本作の最大の魅力は、やっぱり熊徹と九太の関係性。二人の関係って、ただの「師匠と弟子」じゃなくて、親子愛の形そのものなんですよね。
口は悪いけど誰よりも九太を想ってる熊徹。最初は反発してたけど、いつの間にか「自分の生き方」を熊徹から学んでいく九太。血のつながりがなくても家族になれる、そんなメッセージが温かくて胸に残ります。
特に熊徹が消えた後、九太の中に剣として生き続ける展開は「親の愛は形を変えても残る」っていうテーマを象徴してて泣けました。
② 渋谷と渋天街が象徴する「現実と異界」の対比構造
舞台の選び方にも意味があります。渋谷は現代社会の象徴、そして渋天街はもう一つの心の世界。細田監督は「自分が慣れ親しんだ街にこそワクワクする世界がある」と語っています。
実際、渋谷の雑多な空気とバケモノの世界の温かさは、まるで孤独とつながりの対比みたいですよね。九太が行き来することで、「現実と心の成長」が重なって描かれているのがすごく印象的です。
また、昼の多い渋天街と夜の多い渋谷という陰陽構造の演出も地味に深い。こういう細かい演出に気づくと、一気に評価が変わるはず!
③ Mr.Children『Starting Over』が物語を締めくくる余韻
主題歌のMr.Children『Starting Over』も名曲中の名曲ですよね。歌詞の中にある「失敗を恐れずに何度でも立ち上がる」というテーマは、まさに九太の生き方そのもの。
エンドロールでこの曲が流れる瞬間、九太の旅がひと区切りついたような切なさと希望が同時に押し寄せてきます。映像・音楽・物語がピッタリ噛み合う、映画としての完成度を感じました。

チコの正体と楓の存在に隠された意味
この作品で地味に気になるのが、ふわふわした白い生き物チコと、後半で登場する女子高生楓の存在ですよね。
どちらも出番は少なめなのに、ストーリーを大きく左右する重要キャラなんです。特にチコの正体や楓の役割については、SNSでも「意味がわからない」「いらなかった」と議論が絶えません。
でも、実はこの二人こそが九太の心の成長を象徴しているんです。ここでは、二人の存在に込められた深いメッセージを解き明かします。
① チコ=母親の転生説を裏付ける伏線
まずチコの正体。これはファンの間でも有名な考察ですが、実は亡くなった母親が転生した姿だという説が濃厚です。
理由は簡単で、チコは常に九太のそばにいて、彼が闇に飲まれそうになるときにだけ現れる。つまり、「母の愛の象徴」なんです。
さらに、熊徹が倒れたときに九太を止めたのもチコ。暴走しそうな彼を救う行動は、「母が子を叱る」ようにも見えます。この存在がいたからこそ、九太は完全に闇落ちせずに済んだんです。
② 「楓いらない」と言われる3つの理由
一方で、ヒロインの楓には厳しい意見が目立ちます。「足手まとい」「正義感の押し売り」「キャラが弱い」など、ちょっと不憫なくらい(笑)。
確かに後半の展開で九太と一緒に動くシーンでは、危険に突っ込むタイプのヒロインに見えちゃうんですよね。でも、それって実は彼女が“人間の象徴”だからなんです。
楓は「知識」や「社会性」を象徴するキャラ。渋天街で育った九太にとって、楓は初めて出会う“現実の世界の導き手”なんです。つまり、彼女の存在は物語を締めくくるために不可欠だったんですよ。
③ 楓の存在が九太を人間に戻す“導き”であった可能性
九太がバケモノの世界に馴染みすぎていた頃、もし楓に出会わなかったら、彼はずっと渋天街に残っていたかもしれません。でも、彼女と出会い、“勉強”や“未来”というキーワードに触れたことで、再び人間としての自分を取り戻していくんです。
だから、楓は単なるヒロインじゃなくて、九太の成長の象徴なんです。バケモノの世界で心を鍛え、楓との出会いで頭を鍛える。「心と知の両立」こそが彼の物語のゴールだったのかもしれません。

白鯨とクジラの象徴性|闇と光の対比構造
『バケモノの子』を語る上で外せないのが、終盤に登場する巨大なクジラの存在。あれ、最初観たとき「なんで急にクジラ!?」って思いませんでした?
実はこのクジラ、単なるモンスターじゃなくて、心の闇の象徴なんです。そして、そのモチーフになっているのが、アメリカ文学の名作『白鯨(モビー・ディック)』。
つまり、九太と一郎彦の戦いは、“自分自身との戦い”を文学的に描いた構造になっているんです。
① 一郎彦が“クジラ”になる意味とは?
一郎彦がクジラの姿になったのは、彼の闇が具現化したから。尊敬する父に似たいのに、実は人間だった…という現実を受け入れられず、コンプレックスが爆発してしまったんです。
楓が作中で語る「クジラは自分を映す鏡」というセリフがまさにその通りで、クジラ=一郎彦自身。彼が自分を憎むあまり、“自分の闇に飲まれた存在”になってしまったというわけです。
② 九太が闇に飲まれなかった理由
対して九太は、同じく人間でありながら闇に飲まれなかった。その違いは何かというと、彼には支えてくれる人がいたからです。
熊徹や多々良、百秋坊、そして楓やチコ。さまざまな愛情や導きが、九太の心の中に“光”を灯していたんです。
だから彼は、一郎彦とは真逆の選択をした。つまり、“闇を抱えながらも受け入れる”という強さを見せたんですね。
③ 『白鯨』との文学的関連性とテーマ性
細田守監督が『白鯨』を引用したのは偶然ではありません。『白鯨』は、人間が「見えない恐怖」=自分の中の闇と戦う物語。そして『バケモノの子』では、それを現代版の形で描いているんです。
つまり、一郎彦がモビー・ディックであり、九太がエイハブ船長。だけど結末は逆。九太は闇を滅ぼすのではなく、受け入れて前に進む。この違いこそ、現代社会に向けたメッセージなんです。

『バケモノの子』の本当のテーマ|“強さ”と“成長”の物語
ここまで物語の構成やキャラクターを振り返ってきましたが、『バケモノの子』の核心にあるのは“強さとは何か”という問いです。
熊徹も九太も、最初から強かったわけではありません。むしろ、ぶつかり合いながら不器用に成長していく過程こそがこの作品の真の魅力なんです。
ここでは、彼らが見つけた“本当の強さ”の形を、修行・愛・闇という3つの視点から読み解いていきます。
① 「強さとは何か」を問い続ける修行の旅
『バケモノの子』の物語は、まさに強さを探す旅。熊徹は力だけを信じ、九太は心の強さを求めていました。最初の頃は殴り合いと口ゲンカばかりで、まるで父と反抗期の息子(笑)。
でも、そのぶつかり合いの中で九太は「相手を倒すための力」ではなく、「誰かを守るための力」を学んでいきます。熊徹もまた、弟子を持つことで自分の弱さを知るんです。
修行とは、ただ技を磨くことじゃなく、自分の中にある“闇”と向き合う時間。強さ=心の成熟というメッセージが、この作品全体に貫かれています。
② 熊徹の愛が九太を導いた“心の剣”の意味
物語のクライマックスで、熊徹は神となり、九太の胸の中の剣になります。これが象徴しているのは、愛が力に変わる瞬間。
熊徹の教えや存在が九太の心に根付き、それが“剣”という形で彼を守る――この描写、まさに無償の親の愛そのものですよね。
熊徹は消えても、九太の中に生き続ける。この構造は、「愛とは形ではなく、心に宿るもの」というメッセージをストレートに伝えてくれます。強さとは、“愛を背負って生きる覚悟”なのかもしれません。
③ 闇を受け入れて成長する“人間の強さ”とは
九太は最後、心の中の闇と真正面から向き合います。逃げずに受け入れることで、彼はようやく“人間としての強さ”を手に入れるんです。
この作品が伝えたかったのは、「闇をなくすこと」じゃなく、「闇と共に生きる力」。自分の弱さを認めることが、真の強さにつながるというテーマが、九太の成長を通して丁寧に描かれています。
熊徹も九太も、不完全だからこそ魅力的。完璧じゃないからこそ、そこに“人間らしさ”があるんですよね。

映画『バケモノの子』ネタバレまとめ|ひどい評価の裏にある感動の真実
ここまで「ひどい」と言われる理由を掘り下げてきましたが、結論を言うと、この映画は決して“ひどい”作品ではありません。
むしろ、見る人の人生経験や価値観によって感じ方が変わる深い物語なんです。
最後に、この映画の本質をまとめながら、改めて“感動の真実”を振り返っていきましょう。
① 「ひどい」と感じる部分も実は“成長の過程”
テンポが速い、説明が少ない――確かにそう感じる場面もあります。でもそれって、九太が混乱しながら成長していくリアルさでもあるんです。
人生だって、スムーズに答えが出ることばかりじゃない。『バケモノの子』は、そんな“もがく時間の尊さ”を描いた作品なんです。
② 熊徹と九太が教えてくれる“親子の形”の多様性
血が繋がっていなくても、心が繋がっていれば家族になれる。熊徹と九太の関係は、その象徴ですよね。
親って、完璧じゃなくていい。ぶつかって、悩んで、それでも支え合う。そんな「新しい家族像」を描いたのが、この作品の一番の魅力だと思います。
③ 『バケモノの子』は人生の闇と向き合う全世代へのメッセージ
この映画のテーマを一言で言うなら、「自分の闇を受け入れる勇気」。それは子どもだけじゃなく、大人にも刺さるメッセージです。
細田守監督自身も、「大人こそ、もう一度成長できる」と語っていました。だからこそ、この作品は年齢を重ねるごとに見方が変わる映画なんです。
もし最初に観て「ひどい」と感じた人も、今もう一度観直してみてください。きっと、あのクジラのシーンが全然違って見えるはずです。

- ★ 『バケモノの子』が「ひどい」と言われる主な理由は、後半の展開の急さや一郎彦の動機不足など、物語構成のテンポに関する部分が中心。
- ★ 一方で、熊徹と九太の師弟関係には“もうひとつの親子愛”が描かれ、観る人によって強く共感を呼ぶ要素となっている。
- ★ チコと楓は九太の心の導き手として登場し、「人間としての成長」を象徴する重要な存在であることが明らかになった。
- ★ クジラは心の闇の象徴であり、九太と一郎彦の戦いは“自分自身との対話”をテーマにした象徴的なシーンとして描かれている。
- ★ 『バケモノの子』は、闇を受け入れながら成長していく人間の強さを描いた、全世代に響く普遍的な物語である。



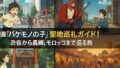
コメント